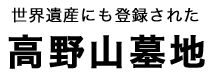山岳霊場である高野山は、元々あった日本人の民俗信仰といえる先祖信仰と、外国からの密教が調和しているのが特徴。
弘法大師が816年に高野山開創の許しを得て、高野山に結界を結び、聖なる空間に。
そして835年に弘法大師が永遠に生きて人を救いたいという願いのもとに入定した御廟(ごびょう)を中心に先祖信仰の場が広がっている。
江戸時代には、大名の約半数が高野山に供養塔を建てている。
材料の石は明治時代までは大阪などで作り、九度山まで船で、その後は人の力で2日間かけて町石道を運んでいたという記録も残っており、
高野山の墓は文化財ともいわれている。
実際、墓石のコンクールを垣間見ることができるほどである。
|
墓地所在地は、変更になっている場合があります。
| トップページへ戻る |