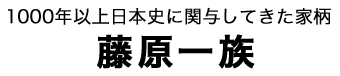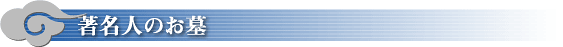
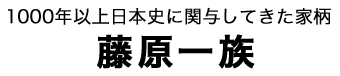
元を中巨氏と称し、大化の改新に功のあった鎌足が藤原の姓を賜って以来藤原氏の祖となった。
初代藤原の次男・不比等は大宝律令の選集、また娘・光明子を皇后にたてるなどで藤原氏隆盛の基礎を作った。
これより朝廷との姻戚関係が続き、日本の朝廷政治に関与することとなった。
一時南北に分かれたが、後に北家の方が主流となり、摂家・関白・太政大臣など平安朝末期まで独占する家柄となる。
鎌倉時代以降は武家政権の台頭により勢力を失っていった。
その後、五摂家と呼ばれるすなわち、近衛・鷹司・九条・二条・一条に分かれて江戸時代に入り、家柄の存続は明治まで続く。
中には土佐の一条房元、伊予の西園寺実充のように戦国大名、それから江戸時代の大名になった者もある。
安政の大獄を行った井伊直弼、キリシタン大名で有名な大友宗麟や大友氏と同じ九州の大名龍造寺家・鍋島家も一族である。
他にも日野富子で有名な日野氏や、三条・西園寺・冷泉等も一族であり、藤原一族が日本民族に与えた影響は計り知れない。
世界史上まれな1000年以上にわたって日本の政治に関与してきた家柄。墓に関しては作り続けて1200年の重みをここに感じる。
| 戒名 |
ー |
玉垣 |
ー |
| 職業 |
ー |
境石 |
ー |
| 没年齢 |
ー |
竿石 |
ー |
| 所在地 |
京都府宇治市 |
石質 |
ー |
| 墓の方位 |
ー |
墓のスタイル |
ー |
| 正面入り口の方位 |
ー |
台座 |
ー |
|
1987年現在の資料に基づいております。