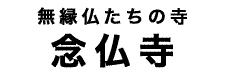七千八百余基の石仏石塔が整列配祀されている。頭部は板石で三角形につくられているものが多く、大部分が規格にはまっている。
仏像の方は、弥陀と地蔵で浄土教系である。室町時代の五輪の塔・鎌倉時代の舟形光背・江戸期の宝篋印塔など、歴史を感じさせる。
エピソードは数多くあるが、明治三十七年の並べかえが最も有名であろう。
岡山の中山通幽という人が、野にさらされ、山に埋まっているものを集めて供養したという。
この辺一帯は賽の河原で死体の捨て場所であったそうだ。庶民には墓など無い時代。
徒然草に出てくる“あしだ野の露消えるときなく……”がそれである。
年二回の供養は、ほのぼのとした血の通いを感じさせて微笑ましくさえある。しかも無縁仏のオンパレード。
こんなに愛され親しまれている墓所は日本にはあまりない。
|
墓地所在地は、変更になっている場合があります。
| トップページへ戻る |