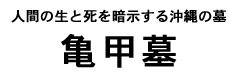亀の甲羅に似た墓で、沖縄にのみ残っている墳墓である。漢時代の中国から伝わったもので、別名「門中墓」とも呼ばれている。
「門中」とは墓を共同にする親族集団のことである。
その門中墓だけあって大きく、炭焼き窯か陶磁器の窯に似ていて、人が充分入れる大きさである。
墓の正面にある入り口は、人一人しか入れないようになっている。いつもは石扉をしっくいでぬり込めている。
この墓の趣は仰臥した女体で、両膝をたてている姿だという。従って死とは、先祖の母体へ還ることを意味する。
死んだ人は、みんな現世を忘れて戻るのだという。墓の前には花や装飾品などはいっさいなく、
盆か正月に一族が集まって酒を飲むくらいで定まった祭礼はないという。
納骨されたものは、没年月日などを記されて、骨壺に納められている。
|
| トップページへ戻る |