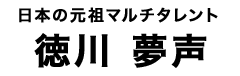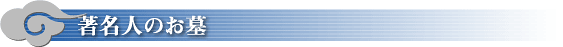
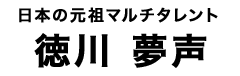
本名は福原駿雄(ふくはら としお)。「彼氏」「恐妻家」の造語でも知られる。
日本放送芸能家協会初代理事長。
1894年4月13日生まれ。
島根県益田市に生まれ、東京に育つ。
口演童話家として活躍し、児童文学の普及に貢献した天野雉彦は叔父。
3歳の頃、母に捨てられ、同居していた祖母に育てられる。幼少の頃から話術が達者で当時演じられていた落語をほとんど覚えていたという。
東京府立第一中学校(現在の都立日比谷高校)を卒業、一高(現在の東京大学教養学部)の入学試験に二度失敗。明治大学の聴講生になったが、憧れの落語家になるため三遊亭圓子の元に入門を決意。
1921年(大正10年)5月14日、日本で初公開のドイツ表現派の映画『カリガリ博士』の弁士を務めたという記録もあり、活動写真が好きでなかった竹久夢二なども観覧し、その印象を雑誌「新小説」に挿絵とともに寄稿。
1925年(大正14年)、新宿武蔵野館に入る。東京を代表する弁士として、人気を博す。
1926年(大正15年)に古川ロッパらと元弁士らの珍芸劇団「ナヤマシ会」を結成。
1933年(昭和8年)、やはりロッパらと劇団「笑の王国」を結成するも意見の相違ですぐに脱退。
1937年(昭和12年)、岸田国士、杉村春子らの文学座に参加。ただし、新劇俳優としての夢声については悪評の嵐であり、文学座を退団。他に、映画にも俳優として出演する。
また、漫談の研究団体「談譚集団」を結成。
さらに、ラジオでも活躍。1939年から、NHKラジオで吉川英治の『宮本武蔵』の朗読を始め、人気を博す。独特の「間」は夢声独自のものであった。
文筆に優れ、「新青年」などにユーモア小説やエッセイを多数執筆。
1938年(昭和13年)、1949年(昭和24年)の直木賞候補にもなった。

俳句好きで、1934年(昭和9年)から久保田万太郎が宗匠の「いとう句会」に所属し、句歴三十年に及んだ。
日々、詳細な日記をつけており、その一部は『夢声戦争日記』として出版され、戦時下の生活の貴重な資料となっている。また、自伝や自伝的な書も何冊も出しており、それらの執筆に日記が役立ったと思われる。
第二次世界大戦後は新しいメディアの波に乗り、ラジオ・テレビで活躍した。
1953年(昭和28年)の、エリザベス女王の戴冠式には、特派員として訪英。
また、娘が日系アメリカ人と結婚していたため、その帰りにアメリカにも寄って娘や孫と会い、その旅を著書『地球もせまいな』にまとめた。
1955年(昭和30年)、「年ごとに円熟を示している各方面における活躍」により、菊池寛賞を受賞。
代表作のラジオ朗読『宮本武蔵』は戦後も、1961年(昭和36年)-1963年(昭和38年)にかけてラジオ関東(現・アール・エフ・ラジオ日本)にて放送。
1965年(昭和40年)には愛知県犬山市にオープンした博物館明治村の初代村長となった。
1971年(昭和46年)8月1日、脳軟化症に肺炎を併発して死去。77歳没。最期の言葉は「おい、いい夫婦だったなあ」であった。
| 戒名 |
|
玉垣 |
|
| 職業 |
弁士・漫談家・作家・俳優 |
境石 |
|
| 没年齢 |
|
竿石 |
75cm(石 92cm) |
| 所在地 |
東京都府中市・多磨霊園 |
石質 |
花崗岩 |
| 墓の方位 |
南西 |
墓のスタイル |
|
| 正面入り口の方位 |
南西 |
台座 |
芝+下+上 74cm |
|