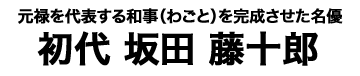1647年(正保4年)、京の座元だった坂田市左衛門(藤右衛門とも)の子として生まれる。
通称は伊右(左)衛門。俳名は冬貞、冬藤。
最近「長政」と呼ばれていたことも判明した。
花車方の杉九兵衛や能小鼓の骨屋庄右衛門らの教えを受けて修行する。
1676年(延宝4年) 11月京都万太夫座で初舞台。
1678年(延宝6年)『夕霧名残の正月』で伊左衛門を演じ、人気を得た。
この役は生涯に18回演じるほどの当たり役となり「夕霧に芸たちのぼる坂田かな」と謳われ、『廓文章』など、その後の歌舞伎狂言に大きな影響を与えた。

その後、京、大阪で活躍近松門左衛門と提携し『傾城仏の原』『けいせい壬生大念仏』『仏母摩耶山開帳』などの近松の作品を多く上演し、遊里を舞台とし恋愛をテーマとする傾城買い狂言を確立。やつし事、濡れ事、口説事などの役によって地位を固め、当時の評判記には「難波津のさくや此花の都とにて傾城買の名人」「舞台にによつと出給ふより、やあ太夫さまお出じゃったと、見物のぐんじゅどよめく有さま、一世や二世ではござるまい」とその人気振りが書かれている。
1695年(元禄8年)には都万太夫座座元にもなった。
1696年(元禄9年度)〜1700年(十三年度)には一座の興行責任者である座本を勤め、芝居作りに励むほか、役者への出演交渉や公儀との掛合いなどにも走り回っている。このころが役者としての最盛期で、次第に病気がちとなり、1708年(宝永5年)10月京都亀屋座の『夕霧』を最後に舞台活動から去り、1709年(宝永六年)63歳で没した。
|
墓地所在地は、変更になっている場合があります。
| トップページへ戻る |