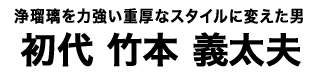1651年(慶安4年)大阪天王寺に生まれる。農家の出身、 江戸時代の浄瑠璃太夫。浄瑠璃の義太夫節の創始者である。初期には清水理太夫と名乗る。

本名五郎兵衛。幼い頃から浄瑠璃に夢中で、10代には芸に優れた者として近郊で名が知られていた。
長じて豪快な語り口が特徴の播磨節創始者・井上播磨掾(じょう)の高弟・清水理兵衛の下で修業を始めたが、浄瑠璃節がどうも自分の気に入らないので、他の浄瑠璃はもとより、当時の様々な「歌い物」「語り物」の長所を採り入れて、いわゆる『義太夫節』を完成させた。義太夫は自らの浄瑠璃を「当流」と呼んだ。
1684年(貞享元年)道頓堀に竹本座を開設し、新派浄瑠璃人形芝居を始めた。
1683年に刊行された近松門左衛門・作の『世継曽我』を上演し、翌年より近松門左衛門と組み、多くの人形浄瑠璃を手掛けた。
1684年(貞享元年)道頓堀に竹本座を建て、新派浄瑠璃人形芝居を始めた。近松門左衛門が座付作者となり、その作を語り、操り人形浄瑠璃を大成した。
1698年(元禄11年)には朝廷に召され、筑後掾の号を賜り、名を藤原博教と改むる宣旨を賜った。
1701年(元禄14年) に受領し筑後掾と称す。
1703(元禄16年)には近松の『曽根崎心中』が好評となって竹本座経営が安定し、座元を引退して竹田出雲に引き継ぐ。
義太夫は竹本座創設の以来約30年間、大坂芸界の牛耳りを執り、当時60余州に於ける芸界の権威であったが、晩年竹田出雲に譲って隠退し、1714年(正徳4年)64歳で没した。
|
墓地所在地は、変更になっている場合があります。
| トップページへ戻る |