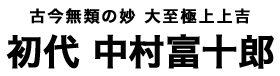1719年(享保4年)生まれ。江戸中期、若くして名人上手と称賛された天才的な女形役者。初代芳沢あやめの3男。俳名慶子。屋号天王寺屋。画号嶺琴舎。
幼少より初代中村新五郎の養子となり、11歳の1729年(享保14)京の佐野川万菊座の色子として名がみえる。その年冬養父と共に江戸へ下り、1731年(享保16年)冬帰京し都万太夫座に出演、
1734年(享保19年)より座本も勤める。
以後女形として三都で活躍。28歳の1746年(延享3年)には評判記の位付けが上上吉となり、31歳で極上上吉にのぼった。
61歳の1779年(安永8年)に大至極上上吉となり、1784年(天明4年)には三ケ津巻首総芸頭という別格に扱われ、その2年後、68歳で没した。
実父芳沢あやめは地芸(演技)を得手としたが、十郎は地芸、所作(舞踊)ともにすぐれた。
少壮期その地芸は地味な写実でしめり過ぎと評されたが、のちそれも改まった。
容姿に恵まれ、時代物も世話物もよく、傾城、娘、奥方、世話女房など広い芸域で高い評価を受けた。
所作事は特に得手で、中でも1753年(宝暦3年)に「京鹿子娘道成寺」を創演したことで知られる。立役を女に改めた「女朝比奈」「女由良之助」「女景清」なども手がけ、晩年には立役を兼ね、荒事も演じた。
多趣味で三味線、琴、茶、香、俳諧などのほか書もよくしたが、特に絵にすぐれていた。性格は柔和で鷹揚、酷暑にも汗ひとつかかなかったと伝える。
「古今天下無双の女方」と評判記で称賛された。2代目富十郎は3代目中村歌右衛門の門人中村松江が継いだ。文政から安政期に活躍した名女形。初代との姻戚関係はない。名跡は平成期の5代目におよぶ。
|
墓地所在地は、変更になっている場合があります。
| トップページへ戻る |