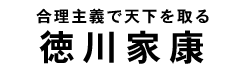戦後の日本で、徳川家康ぐらいもてた人物はいない。その功績は作家山岡荘八氏が「徳川家康」という大長編小説を書き上げたからだろう。それまでは<狸おやじ>とか、<啼かねなら啼くまで待とうホトトギス>で語られた人物だった。けれど、戦後の混乱期、日本の再出発は、家康を手本にすべしとばかりに、山岡荘八氏は書き上げた。これで評価は一変した。家康の生涯は、堅実、律儀、沈着、努力、忍耐、質素、倹約にあったと謳いあげた荘八節には、世の経営者ならずとも、もって瞑すべきことだったのだろう。三河の一大名が天下の覇者になる。関東支配、秀吉との対決、関ヶ原合戦の勝利、そして徳川幕府の体制づくり、人を組織し、時代を動かす先駆者、どれ一つとっても魅力ある人物であった。
人間にはそれぞれ与えられた<運、鈍、根>がある。運とは運命だ。信長の死後は、家康にも天下制覇のチャンスはあった。鈍とは才は才に溺れずだろうか、家康は鈍を武器として、スケールの大きい判断をした。根は努力そのもの、家康の真髄を見る思いがする。いうならばねばり腰だ。信長、秀吉の倒れる時期を長い射程距離においたことだろう。しかも、信長、秀吉が一代かぎりの燃焼であったのに反して、家康は徳川三百年の基礎をつくりあげたのだった。
 |
|
墓地所在地は、変更になっている場合があります。
| トップページへ戻る |