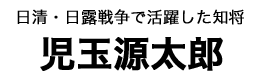1852(嘉永5)年徳山藩士児玉半九郎忠碩の長男として生まれる。
戊辰戦争に藩の献功隊として参加。その後、陸軍に入り、明治31年台湾総督、のち陸軍大臣、内務大臣、文部大臣をもつとめた。このことからも児玉の政治的手腕は抜群であったことがうかがえる。
内務大臣就任後、対ロシアへの外交交渉が始まり、開戦へと向かって行くが、国難に対するため自ら格下(通常は少将)の陸軍参謀次長をつとめた。
開戦後は最初から最後まで満州軍総参謀長として陸軍作戦全般を指導。旅順攻撃では、第3軍司令官乃木希典大将の指揮権を移譲されたうえ勝利を得た。
このときの児玉の指揮は唯一の失敗と言われる黒溝台の戦いを除き、的確に満州軍全般を作戦指導し、奉天会戦・終戦工作等よく務め国難を救ったのである。
終戦後の明治39年、参謀総長在籍わずか4ヶ月、脳溢血で急逝した。54才であった。
児玉は川上操六、桂太郎とともに明治陸軍の三傑と呼ばれた。
墓は背丈より高い竿石が特徴であり、夫婦墓が一墓づつ中央にあり、夫が右で妻が左である。
 |
|
墓地所在地は、変更になっている場合があります。
| トップページへ戻る |