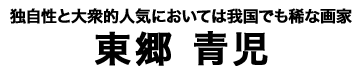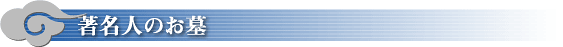
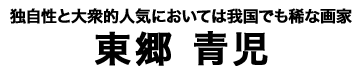
東郷青児(本名は東郷 鉄春)は1897年(明治30年)鹿児島市生まれの日本の洋画家。
独特にデフォルメされ、柔らかな曲線と色調で描かれた女性像が有名で洗練された美意識を感じさせる作風が特徴的であるが通俗的過ぎるとの見方もある。後期には版画や彫刻などの作品も多く手掛けた。青児の名前は青山学院中等部在籍が由来と言われています。
幼少期に一家で東京に転居後、1914年(大正3年)に青山学院中等部を卒業。
1915年(大正4年)頃ドイツ帰りの作曲家山田耕筰の東京フィルハーモニー赤坂研究所の一室で制作で励むかたわら、日比谷美術館で初個展を開催する。この頃有島生馬を知り以後師事した。
1916年の第3回二科展に初出品した『パラソルさせる女』により二科賞を受賞。画壇に華々しいデビューを飾る。
1921年から1928年までフランスに留学。当初トリノに未来派のマリネッティを訪ねて未来派運動に参加する。その後リヨン美術学校で学ぶ。この頃の作品にはピカソらの影響多々が見られる。
1928年帰国後、第15回二科展に留学中に描きためた作品23点を出品し第1回昭和洋画奨励賞を受賞する。
1931年には二科会入会。その後1938年「九室会」が結成されと、藤田嗣治と共に顧問になった。
1957年岡本太郎と共に日活映画『誘惑』に特別出演(西郷赤児役)。またこの頃第13回日本芸術院賞を授与され、第4回日本国際美術展で大衆賞を受賞。
1960年日本芸術院会員になり、1961年には二科会会長に就任する。
1969年フランス政府よりオフィシェ・ドルドル・デ・ザール・エ・レットル(文芸勲章)を授与された。
1976年西新宿に東郷青児美術館(現在の損保ジャパン東郷青児美術館)が開設され、同時に勲二等旭日重光章授与。
1978年4月25日、第62回二科展(熊本県立美術館)出席のため訪れていた熊本市にて、急性心不全のため死去。享年80歳。没後、文化功労者、正四位追贈を受ける。
画風は弟子にあたる安食一雄(あじきかずお)に受け継がれている。
| 戒名 |
|
玉垣 |
前24cm 後60cm |
| 職業 |
洋画家 |
境石 |
30cm |
| 没年齢 |
|
竿石 |
80cm
(幅上35cm 下41cm)
(奥行上34cm 下40cm)
台形 |
| 所在地 |
東京都豊島区・雑司ヶ谷霊園 |
石質 |
花崗岩 |
| 墓の方位 |
東南 |
墓のスタイル |
|
| 正面入り口の方位 |
東南 |
台座 |
上32cm
(幅71cm 奥行71cm)
下33cm
(幅133cm 奥行134cm) |
|