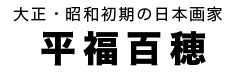平福穂庵の子。
父に画を習い、18歳の時上京し、川端玉章の門に入る。
美校卒業の翌年、日本美術院の理想主義に対抗して、写生主義をとなえ、結城素明らと无声会を組織。この会の中心的存在として作品を発表した。
その間、雑誌や新聞に挿絵を執筆、とくに軽快酒脱な筆致を生かした時事的なスケッチは紙面に生彩をそえた。
1909年第3回文展に「アイヌ」、第8回文展に「七面鳥」を出品、世に認められた。
1916年鏑木清方・吉川霊華らと金鈴会を結成、そして1920年金鈴社となり、同志と研究・作画に精進、日本・中国の古典に対する観照を深めた。
その作風は伝統的な画風を超え、また日本美術院の当時の傾向とも一線を画し、磨きのかかったスケッチ風の筆法を骨格にして、南画の雅趣をたたえた独自の風格をそなえている。
また構図や表現にも古典を現代に生かした独自の手法は、すぐれた素質と力量を示す。
代表作は他に「予譲」「荒磯」「堅田の一休」「春の山」などまたアララギ派の歌人としてもきこえ、歌集に「寒竹」がある。
(参考文献:コンサイス 日本人名事典・ウィキペディア(Wikipedia))
 |
|
墓地所在地は、変更になっている場合があります。
| トップページへ戻る |