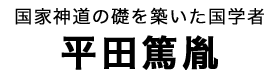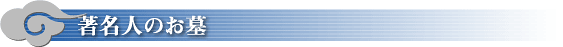
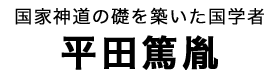
1776(安永5)年、出羽国秋田佐竹藩の藩士の子として生まれる。
父は佐竹藩士大和田清兵衛祚胤。禄高100石の秋田藩士の4男。20歳のとき脱藩して江戸へ出て苦学力行する。
1800(寛政12)年、25歳のとき備中国松山藩士平田篤穂の養子となる。
1801(享和1)年、本居宣長に入門したが宣長の病死に間に合わず、「没後の門人」になったと自称しているが、
学統を主張するための虚実とみられる。
28歳のとき『呵妄書』(1803)を書いて太宰春台批判を企てる。
1804(文化1)年、真菅乃舎開業。そして本居宣長の学業を学び、勤勉に学につとめ『新鬼神論』『古道大意』『俗神道大意』などを書きあげた。
その上で『王襷』『古史徴』『古史伝』の構想をねり上げている。『霊の真柱』の刊行は広く宣長門の注目をあびた。
その後、門下は江戸の下町を中心にしだいに関東へと波及する。
その後も著述はつづくが、しだいに江戸の民俗の基層社会へ接近する。
しかし、激しい儒教批判と尊王思想のため幕府の忌むところとなり、1843(天保14)年、秋田へ追放され病死した。
頑固で自己主張の激しかった篤胤。明治維新の思想的原動力ともいわれた人物だったが、性格の激しさが自然石の墓に出ているようである。
| 戒名 |
神号:神霊能真柱大人 |
玉垣 |
ー |
| 職業 |
江戸時代後期の国学者 |
境石 |
20cm |
| 没年齢 |
67歳 |
竿石 |
102cm |
| 所在地 |
秋田県秋田市・千秋公園 |
石質 |
自然石系 |
| 墓の方位 |
南 |
墓のスタイル |
自然石 |
| 正面入り口の方位 |
南 |
台座 |
|
|
1987年現在の資料に基づいております。