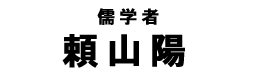一冊の本が人生をかえるとよく言われる。頼山陽の『日本外史』ぐらい幕末の志士たちに読まれた本はない。維新の大業を促進させた原動力として、この本の影響力は大であるという。
父・春水が神童といわれた人で、山陽は生まれながら学者の家に育ったことになる。幼年期は、“門前の小僧習わずお経を読む”のたとえ、寝食を忘れて読書をしていた。十九歳で江戸昌平黌に入り、当時の教授である柴野栗山に見込まれたが、彼の秀才ぶりはもう師を不要としていたため、翌年には郷里の安芸国(広島県)に戻ってくる。
並外れた人物で、脱藩までして学問の道へ進んだ。後世に残る『日本外史』は、脱藩事件の後に着稿。本来なら重罪で死刑なのだが、藩主は山陽の人物を愛し、寛大にも三十両の手元金まで下賜して、山陽の前途を優しく見守ったという。
山陽のお墓は、広い場所であるが、同族墓で祀り方が意外と乱雑である。統一性がなく、他人のお墓も存在する。
 |
|
墓地所在地は、変更になっている場合があります。
| トップページへ戻る |