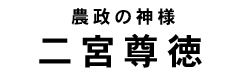戦後になるまで、全国の小学校に、薪を背負い、本を読んでいる銅像が校庭に建てられていた。その人物が二宮尊徳であった。片時も惜しんで勉強に励む姿は、教育界にとっては格好の人物にちがいない。
幼名を金次郎といい、五歳のときに大洪水に会い、地主だった彼の生家は一挙に奈落の底に転落、貧しい生活を送ることになる。
成人して金次郎は、小田原藩服部家若党になり、文化十二年、服部家の家計立直しに参加、農政家としての実力を示しはじめた。その後、幕臣にとりたてられ、後に報徳運動の基礎を作りはじめた。天保二年(一八三一)には、櫻町領収納を約二倍にまで再興したことなどから、各藩から引っぱりだこになり、晩年は幕府より日光領地の開拓調査を命じられ、没年までこの難事業と取り組み、農政家としての手腕を認められていた。
尊徳は遺言で「余を葬るに分を越ゆることなかれ、墓石を立てることなかれ。」としたそうだが、実際はその遺言は守られていない。
 |
|
墓地所在地は、変更になっている場合があります。
| トップページへ戻る |