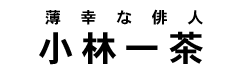一茶は運命的には薄幸の人である。実母は三歳の時に死去。祖母には可愛がられたが、七歳の時、継母がきて仙六という弟ができてから、ひねくれ者になったという。祖母が死んだ翌年、継母との折り合いが悪く、江戸へ奉公に出される。心の安らぎを求めて、俳諧師・二六庵竹阿の門を叩き、九年後に“一茶”の号を貰った。
三十八歳の晩春、一茶が故郷に帰ってみたら、父が病に倒れていた。一ヶ月の看病記録が、有名な『父の終焉日記』である。父への敬愛、継母や弟に向ける憎しみの記録である。初七日の日、父の遺言「財産は兄弟均等に分けるよう」を守るといった継母の言葉を信じて江戸に帰ったが、弟は一茶の思いをはねつけた。弟との談判は、江戸奉行所に訴え出るまでの争いになり、それをみかねた明専寺の住職が仲に入り、一茶は三十五年もの漂浪生活も終ったと思い妻をもらったが、初婚は九年目で妻の死をもって終焉。四人生まれた子のうち三人を失うなど、晩年の苦しみは目にあまるほどである。
 |
|
墓地所在地は、変更になっている場合があります。
| トップページへ戻る |