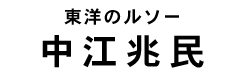約100年前、日本においてルソーの『民約論』を翻訳したのが中江兆民である。明治の人々が西洋の思想にふれ、自由民権運動の原点であるといわれる。そして、また民衆の政治への参加とともに、啓蒙書の翻訳者としての兆民の名声は高まっていた。彼が主宰した啓蒙誌『政理叢誌』は、単にルソーだけでなく、西欧の自由主義的な文献一般の紹介など、インテリ層にとって大いに好評だった。兆民は西洋思想のパイオニア的な存在であった。
その兆民だが、土佐藩・高知城下山田町、下級武士の中江元助の長男として生まれた。3歳頃には読み書きをする天才児だった。あまりの才能に、藩は彼を長崎へ留学生として送る。その長崎で維新前後歴史を騒がせた坂本龍馬、藩の主導者後藤象二郎、明治の経済界の立役者岩崎弥太郎(三菱の創始者)らと交友を結んだ。それらの人物の中でもとりわけ坂本龍馬の感化により、兆民は目覚めたようだ。
活動期の兆民は、自分の才能をフルに生かした。語学が彼の力である。兵庫港海港の際のフランス公使の通訳官。フランス留学(フランス法研究の司法省留学生)の時に、教師も舌をまき、フランスに永住してジャーナリストにならないかといわれたほどの語学力だった。帰国後は、政治評論をはじめ、数々の優れた学問的業績を残している。
墓の姿は、細長い墓石は自然石に近く、石を少しだけ加工した感の高さ。台石との調和もない。坂本龍馬の墓と同類のスタイルだろう。
 |
|
墓地所在地は、変更になっている場合があります。
| トップページへ戻る |