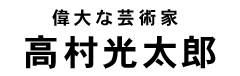明治・大正・昭和三代にわたって活躍した高村光太郎は詩人として、また彫刻家としての芸術家の名をほしいままにした。
光太郎は4歳ごろまで病弱であった。小学校の7・8歳の時分に、仏師であった父から切り出し・丸刀・間透など3本ばかり貰った。
好むと好まざるとによらず、彫刻家への道へ引きずり込まれた。
15歳に東京美術学校予科(日本画)に入学。知識欲は人一倍、あらゆる事を吸収するため、図書館通い、英語を正則英語学校にて学び、歌舞伎や落語にも興味を持ち、ボディビル・鉄棒・弓で体を鍛え、身心両道を学び続けたという。
明治35年7月、20歳で美術学校の木彫科を卒業した光太郎は、そのまま研究科に残り、研究に励んでいたが、同38年モークレールの『オーギュスト・ロダン』の英語本を手に入れ、彼の芸術開眼がなされた。と同時に文学的な表現・詩作に興味を持ち始めたのもその頃であった。
24歳の時にアメリカへ、そして憧れのパリへと光太郎の芸術遍歴の旅は続く。彼は『暗愚小伝』中の「パリ」で、「私はパリで大人になった。はじめて異性に触れたのもパリ。はじめて魂の解放を得たのもパリ・・・」と謳いあげている。
そして結婚、妻智恵子の死、芸術的ないくつもの受難、死ぬまで崇高な芸術を求めて止まなかった光太郎。詩集『典型』扉の「手の彫刻」は、彼の生涯を語る道程だっただろう。
墓は、光太郎。光雲(父)、豊周(弟)三人によるデザインである。
竿石が太くて短く、周囲は樹木で覆われている。
彼は死の4日前「The end か! 人間の一生なんて・・・」という言葉を残している。
 |
|
| トップページへ戻る |