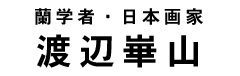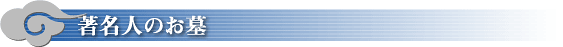
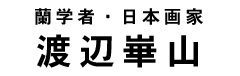
幕末には様々な人物が活躍していたが、渡辺崋山もその一人で、田原藩家老、蘭学者、日本画家といった多才ぶりであった。
青年期までは貧乏に悩まされていたが、彼の向学心は貧乏に負けなかった。
努力家で、決心したことは何事でも貫く崋山は、1832年田原藩の年寄末席に命じられ、江戸詰の生活をすることになった。
江戸に出てからの崋山の知識欲は大変なもので、天保四年(1833)には「尚歯会」結成、内外情勢の研究に熱を入れ、
あげくのはて退役願いを出し、国事に奔走、海防を主張し、海外事情の先駆者的な著書を発表して幕府を批判。
天保十年(1839)、捕らえられて投獄された。
時代を先取りした崋山、許されて故郷に帰され、蟄居生活。そのはけ口を絵画に求めていったが、
弟子が崋山の生活援助にと開いた画会が問題となるに及んで、自殺した。残された彼の仲間は開港の準備に力をそそいだという。
| 戒名 |
文忠院崋山伯登居士 |
玉垣 |
60cm |
| 職業 |
江戸後期の画家・思想家・藩政家 |
境石 |
- |
| 没年齢 |
49歳 |
竿石 |
80cm |
| 所在地 |
愛知県渥美郡・城宝寺 |
石質 |
灰色、軟石 |
| 墓の方位 |
北東 |
墓のスタイル |
普通 |
| 正面入り口の方位 |
北東 |
台座 |
3段・高さ65cm |
|
1987年現在の資料に基づいております。