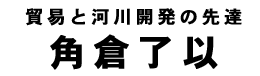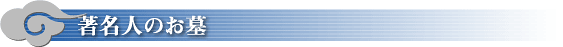
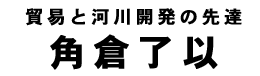
京都市千光寺に残る角倉了以の木像は、石割斧を手にして座っていて、一文字に結んだ口と鋭い眼差しは威圧的でさえある。
彼の激しい性格を物語っているといえよう。
了以は医者の家系に生まれたが、医者になることを嫌って、算数と地理を学び、諸外国との交易に着目した。
文禄元年(一九五二)には豊臣秀吉から朱印状を受け、安南と貿易を始め、巨万の富を手にする。
角倉船は、了以が死んでからも子に受け継がれ、鎖国までつづいた。
了以が情熱を傾けたもうひとつの大事業が、国内の河川開発である。
大堰川の川ざらえは、それまでいかだで運搬していた米や塩・木材などを船で自由に運ぶことができるようにし、
沿岸の民衆に利益をもたらした。富士川の水路工事においては、
この業績を知った家康がその実力にいたく感心したということを伝える書状も現存している。
立派な墓所に、先祖ともども眠っているが、一番大きい墓が本人の墓である。
| 戒名 |
珪應了以大居士 |
玉垣 |
68cm |
| 職業 |
安土・桃山時代の豪商・海外貿易家 |
境石 |
85cm |
| 没年齢 |
61歳 |
竿石 |
58cm |
| 所在地 |
京都市嵯峨野・二尊院 |
石質 |
花崗岩 |
| 墓の方位 |
東 |
墓のスタイル |
奇型 |
| 正面入り口の方位 |
東 |
台座 |
無 |
|
1987年現在の資料に基づいております。