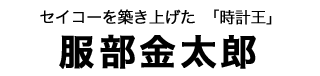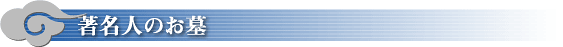
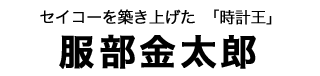
1860年、江戸の貧困な夜店商人の家に生まれる。
13歳より唐物屋に奉公し、1874(明治7)年から時計店に勤め、時計の修繕販売に従事する。
その後、1881(明治14)年に個人経営で時計小売業として服部時計店(現・セイコー株式会社)を開業した。
商売熱心だったため、早くも3年後には「東京時計商繁盛鏡」と言う時計商番付の最下段に登場した。
また、良い商品を仕入れていたため「浜の屋敷(横浜外国商館)」の信頼も得るようになった。
こうして実績を重ね銀座にも進出し、開業6年目にして服部時計店は時計販売の大手に育った。
当時、我が国の時計製造業は未発達ですべて輸入に頼っていたが、1892年に精工舎をおこし、掛時計・懐中時計・目覚まし時計の製造に着手。
欧米の技術を学び国産時計製造業の発展に尽し、ついに外国製品に比肩しうる精巧品の製造に成功した。第一次大戦時には欧米に輸出するに至った。
「SEIKO(セイコー)」はその商標である。「一人一業主義」を守り、始終時計業に専念した。
また赤十字社をはじめ、各種社会事業にも貢献した。1930(昭和5)年私財を投じて財団法人服部報公会を設立した。
墓所の入口が正面ではなく、先祖の墓より大きい。夫婦墓で妻の戒名が正面の左にある。コンクリートで墓地を敷き詰めてあるのも特徴。
| 戒名 |
正道院杜溪日信士 |
玉垣 |
無 |
| 職業 |
明治・大正期の実業家 |
境石 |
60cm |
| 没年齢 |
75歳 |
竿石 |
竿より高い・120cm |
| 所在地 |
東京都府中市・多磨霊園 |
石質 |
花崗岩(白系) |
| 墓の方位 |
東南 |
墓のスタイル |
普通 |
| 正面入り口の方位 |
北東 |
台座 |
3段・高さ約400cm |
|
1987年現在の資料に基づいております。