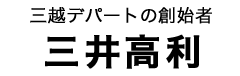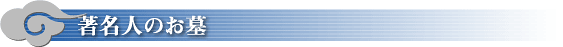
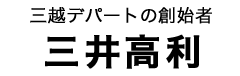
1622(元和8)年、伊勢松坂の商人・三井高俊の四男として生まれる。
父の死後、商才にすぐれた母に育てられ、14歳で仕入店を京都において江戸で広く小間物をあつかう長兄・俊次の店に修業に入った。
やがて自ら独立を望んだが長兄に反対され、また、三兄・重俊が没した為、代わって母を孝養するという理由で松坂に帰郷。
家業を継いで金融業と商業に手をのばした。
長兄の死後、1673年(延宝元)に江戸の本町1丁目(東京都中央区)に念願の呉服店越後屋を開いた。
高利はこの新装の越後屋(後の三越)を息子達に預け、
自らは伊勢で総指揮を執る。
また、商法改革を行い、それまでの呉服店の商慣習だった得意先からの注文後に好みの品物を特産する
「見世物商い」や得意先のところへ商品を持参する「屋敷売り」、そして代金の6月・12月のニ節季払い、
或いは十二月の極月払いによる決済方式を一掃し、
諸国の商人への卸売り(「諸国商人売」)や店頭での小売・切り売(「店前売」)、現金掛値をなくした薄利多売の方式を編み出した。
この方法により資金と商品の回転がすみやかになり、当時の都市社会に新しく勃興しつつあった「町人」という階層を対象とした
大量の取引きを可能にした。
1694(元禄7)年、73歳で没。彼一代で三井は当代屈指の豪商となり、のちに「三井財閥の祖」と称された。その遺産は彼個人の分だけで約4900貫(金8万両相当)と推定されている。
三井家の墓所は初代三井高利を除き、質素を旨とした。さらにニ代目からは同じスタイル、同じ寸法で建てている。これこそ財を引き継ぐポイントかもしれない。
| 戒名 |
松樹院長誉宗寿居士 |
玉垣 |
75cm |
| 職業 |
江戸時代の豪商 |
境石 |
芝石10cm |
| 没年齢 |
73歳 |
竿石 |
120cm |
| 所在地 |
京都府京都市・真正極楽寺真如堂 |
石質 |
白系花崗岩 |
| 墓の方位 |
北西 |
墓のスタイル |
位牌型 |
| 正面入り口の方位 |
北西 |
台座 |
|
|
1987年現在の資料に基づいております。