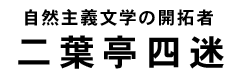四迷の作品『浮雲』は、明治中期の文学としては、群を抜いていた。
西洋文学を読み、とくにロシア文学、ツルゲーネフ、ドストエフスキーの愛読者だった彼は、
日本の自然主義文学のパイオニアになりうる素地を持っていたといえよう。
少年の頃は軍人志望だったが、途中から外交官になる夢を持った。
そのため外国語学校に入り、ロシア語を学んだ。
将来ロシア公使になることを心の中で誓っていた。
ところが、いつしか文学の道へ入りこんでしまい、ツルゲーネフを翻訳していた。
が、晩年は文学嫌いになり、国際問題の研究者たらんと方向を変えていった。
朝日新聞ロシア特派員になって、同地に赴いたが、過度の神経衰弱にかかり、不眠症に悩まされ、
ロシア人医師の診察を受けたところ、肺病の末期、急いで帰国の途についたが、インド洋ベンガル湾上で帰らぬ人となった。
享年四十八歳、男ざかりの死去だった。
四迷は学生時代から変わり者で茶目っ気なところがあったという。
変装旅行が好きで、晩年の写真もロシア帽にヒゲ、別人の姿に変装している。
墓の姿も変わっていて、洋式墓とでもいうべきか、板石の墓である。
 |
|
墓地所在地は、変更になっている場合があります。
| トップページへ戻る |