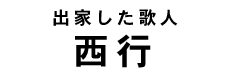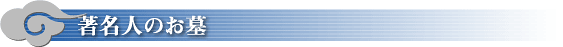
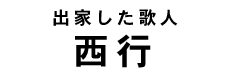
西行の歌の総数は三千百十二首もあるといわれている。
中には外交辞令的な贈答歌も含まれてはいるが、歌人としては超一流の人物である。
『万葉集』とならび称せられる『新古今和歌集』の中で、第一位、九十四首が取りあげられていることからしても、その評価は高い。当時としては官位も、僧位としても低い西行であった。
彼が伊勢神宮の神官たちに作歌指導した折、「歌は心の数寄で詠むべきなり」と説いたが、
歌に対する西行の基本姿勢がうかがえる。
鳥羽院(上皇)の下で北面の武士として仙洞御所に勤務し、十九歳の頃、歌人として最初に認められたとされている。
妻や子があったというが定かでない。
出家の原因は、高位の女官との恋に破れたためといわれているのが定説である。僧の道を歩み始めてからも、時の権力者たちや女房連の歌の指導役をおおせつかっていたことが高じて、忍者もどきの歌人として諸国をさすらう破目になった。
彼の死の前年二月に詠んだとされている句がある。
願はくば花の下にて春死なん
そのきさらぎの望月のころ
西行の墓は、この歌の通り、たくさんの桜の木がある所に祀られている。
| 戒名 |
- |
玉垣 |
無 |
| 職業 |
平安後期の歌人 |
境石 |
無 |
| 没年齢 |
73歳 |
竿石 |
自然石 |
| 所在地 |
大阪府河南町・弘川寺 |
石質 |
自然石 |
| 墓の方位 |
東南 |
墓のスタイル |
墳墓と自然石 |
| 正面入り口の方位 |
東南 |
台座 |
自然石 |
|
1987年現在の資料に基づいております。